アーティスト、アマとプロの違いは?ニューヨークは芸術家にプロの定義がある?
彫刻家の大黒貴之(@takayuki_daikoku)です。
「ニューヨーク―芸術家と共存する街」という本をご存知ですか?
1999年に出版されたニューヨークでの芸術家と彼らを取り巻く社会環境のことが主に書かれている本である人に紹介してもらって読んでみました。
具体的かつ、聡明に書かれているので、とてもわかりやすい本です。
ニューヨークにはプロの芸術家の定義がある?

「プロの芸術家」とは、一体どういう人のことなのでしょうか。日本では、芸術家のプロとアマの境界線が、曖昧すぎます。だから誰でもアーティストやなんでもアートになってしまいます。
ところが、この本を読んで衝撃を受けたのは ニューヨークでは、「プロの芸術家」という定義をちゃんと設けているということ。そして、作品を売って食べている人だけがプロの芸術家という認識ではないのだということです。
プロの芸術家としての証明書

未國「BONSAI 2012 Berlin」Photo:Takayuki Daikoku (本文のイメージ写真です)
ニューヨークでは、ニューヨーク市文化局という機関があって、そこがプロの芸術家としての証明書を発行しているという。
では、具体的にどのような人がプロの芸術家と認知されるのかというと
(以下抜粋)
1.商業的芸術ではなく、純粋芸術
ーすなわち絵画、彫刻、振付、映像、作曲等 その他を含むものー
の創作を不断に進行させている個人。2.自己の表現形態に真剣かつ不断に傾倒してきたことを証明できる個人。
3.現時点でも、その表現形態に専心、従事している個人。
ここいう、「専門の職業(プロフェッショナル)」とは、
その者が生涯その表現形態に従事するという
その専心そのものを意味するのであって
その創造行為や努力が金銭的にどれくらいの報酬を
もたらすかという額高の問題ではない。また、プロの芸術家として制作してきた作品の集積が
5年の歳月に及んでない者、および学生、
商業に従事するアーティスト(デザイナーなど)、
趣味の芸術家、芸術制作作品が第一の職業というのでない人などは、
証明書の申請資格はない。(抜粋終わり)
その他にも、たくさんの参考にするべき内容があるのですが、ここでは割愛させていただきます。
芸術家と社会との接点とは
芸術家と社会との接点を考えるとき、アーティストの社会的な環境を整えていくことはますます大事になります。芸術が社会の日常的なものになること。芸術家と社会がもっと結びついていくようになること。それは、社会を多様化させていく上でとても大切なことだと考えます。そのようなことを浸透させていかないと、どれだけ素晴らしい作家や作品、 素晴らしい美術館ができても、その素晴らしさは半減するのではないかと危惧します。
多大な時間がかかることは予測できますが、芸術をもっと社会に浸透させていく活動、つまり芸術、美術、文化のインフラを整えていく必要が日本にはあります。
「ニューヨーク―芸術家と共存する街」もう古い情報になっているかもしれませんが、一読する価値は十分にあると思います。
(2009年5月14日「ニューヨークの芸術家と社会環境」を加筆添削した文章です)
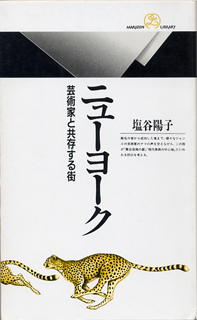





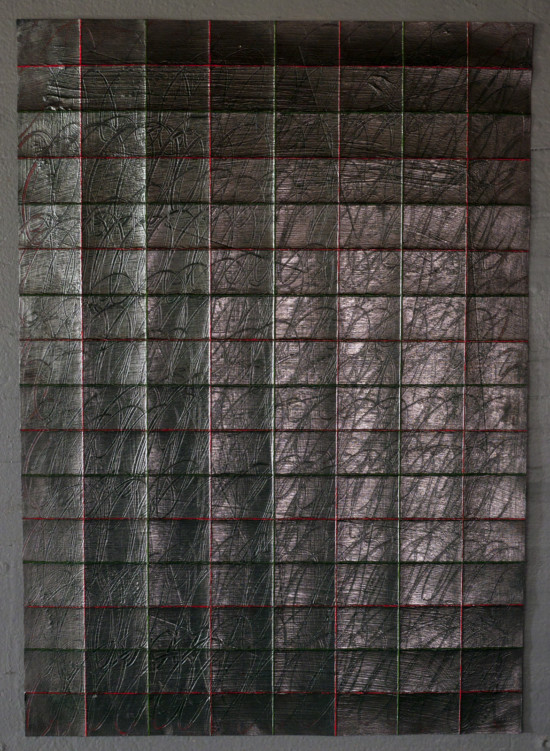


この記事へのコメントはありません。