生物はなぜ死ぬのか:生物の死や多様性の重要性を生物学的に解き明かす名著
彫刻家の大黒貴之(@takayuki_daikoku)です。
小林武彦氏著書の「生物はなぜ死ぬのか」(講談社現代新書)を読み、大変感銘を受けました。死は全ての生物が直面する現象です。特に人間は古今東西、死について恐怖や不安を抱き続けて現在に至っています。「死んだらどうなるのだろう?」「死ぬ直前はどうなるのだろう?」「死ぬ時に後悔しない生き方とはどのようなものなのだろう?」
本書は「なぜ私たちは死ななければならないのか?」という疑問を、生物学的見地から縺(もつ)れた紐を解くように解明していきます。

なぜ私たちは死ななければならないのか?
この地球上に生命が誕生したのも、たくさんの生き物が存在するのも、そして死ぬことも、全てはなるほどと思える「そもそも」の理由があるということです。
自然界を眺めてみると、その生態系はいわゆる弱肉強食でできており、絶妙なバランスで成り立っています。捕食者、食べられる者、そして死んだ生物は分解者によって他の生物の養分となります。このように生と死のサイクルによって自然界は成っています。このサイクルを「ターンオーバー/生まれ変わり」といいます。新しい生命と死んでいく生命の永遠のサイクルとも言えましょう。またこの生まれ変わりのプロセスの途中で、いわゆる変異が起こり、それによって生物はその環境に合わせて進化してきました。
異質なもの同士が並存することは、自然の調和美だと考えます。それは多様性/diversityの美とも言い換えることができるのではないかと思います。多様性の意義は「生物が他の生物の居場所を作り、食料も供給する」ことだと著者は言います。つまり、生態系が複雑であるほど、いろんな生物が生きられる場所ができるということです。ここで重要なのは、このような複雑な生態系は、環境変化などに強いと考えられているといいます。
人間の現代社会に置き換えるとどうなのか?
このことは、私たちが生きる人間社会にも同じことが言えるのではないでしょうか。現在では、大きな物語やイズムはなくなりつつあり、特に民主主義社会は、より小さな物語が多くある状態だと考えます。ユーチューバーやインスタグラマー、プロゲーマーなどの新しい職業やニートという定義は、20年前はありませんでした。また自身の身近な例ですが、私が学生だった20年前に比べると、昨今、現代アートというキーワードをよく聞くようになりました。また若いアーティストが活躍できる場所も増えているように映ります。またLGBT、ブラック・ライブズ・マターなどの言葉が日本でも多く聞かれるようになりました。そう考えると日本の社会にも多様性が少しずつ広がって来ているのかもしれません。
人間社会においても新しい産業や新しい生き方を実践する人たちが現れることによって、新しい考え方や生き方、職業が生まれてくるのだと考えます。実際に、200年前に起こった産業革命では、それまで手工業だったものが機械化され多くの人たちが失業しました。一方で、鉄道、自動車、工業機械などの分野で新しい仕事が生み出されました。90年代に起こったインターネット革命以降誕生した前述のようなデジタル系の新しい職業もまたしかりです。今では、大阪から東京へ向かうのに駕籠(かご)を使う人はいませんし、FAXを使う人もほとんどいなくなりました。また日本で長く根付いていたハンコ文化もデジタル化によって近い将来消えていくでしょう。このような新陳代謝が行われることによって、より複雑な生態系になり、生き方や考え方の多様化によって、しなやかな強さを持つ社会になっていくのではないかと思います。

生物には死という現象は遺伝子に組み込まれていて、それは老化によって死へと近づいていきます。そして、死によって生態系の多様性は維持されると著者は言います。人は、感情や想像力を持つ生物ですから、特に身近な人の死には相当なショックが伴います。私自身も父の急逝の時は、強い衝撃があり長い間生と死について深く考え続けた期間がありました。私もいずれはこの世から去っていくのですが、俯瞰的に眺めると、それらも次世代の社会が健全でしなやかさを備えるための現象だと理解すると死の認識も変わっていきそうです。
また本書では、昨今、よく聞かれる子どもの個性を伸ばすには社会はどのようにするべきか?人はAIとどのように向き合っていくべきか?など、さまざまな著者の見解が述べられています。
今回は、私見も交えながら「生物はなぜ死ぬのか」についての見どころや所感を書きました。もし機会が有りましたら是非手にとってご一読ください。大変機知に富んだ内容で死や多様性についての新しい発見があるかと思います。まさに死生観が一変する現代人のための生物学入門です。
関連記事
参考文献
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。





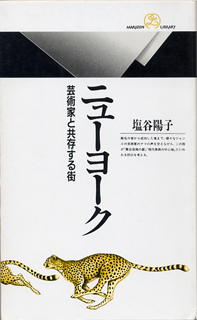



この記事へのコメントはありません。